発達相談から療育を受けるまでの流れを徹底解説!
子どもの発達に心配や懸念があるけれど、どうしたらいいかわからない・・・
子育てをしていると、うちの子は大丈夫かな?と心配になってしまう、そんな方は多いと思います。
複雑に思われがちですが、実は療育へのアクセスは、いたってシンプルです。
今回の記事では、私の娘が1歳2カ月で療育に通うことになった体験談をふまえて、療育に行き届くまでの流れを紹介していきます。
※お住まいの地域や受けるサービスによって差異があると思いますので、流れに個人差があることはご了承ください。
娘の発達について詳しくはこちら↓
ハイハイしないシャフリングベビーの成長記録
娘が療育に通うことになった理由

ハイハイしない、シャフリングベビーだった
はい、そうなんです。
我が娘は、1歳ごろになるまでほとんど寝返りせず、生後9カ月ごろから座ったまま移動する「いざり歩き(通称シャフリングベビー)」をするように。
予想通りでしたが、10カ月検診では、いざりから来る体幹の弱さを指摘され、要観察になりました。
そして、10カ月検診の後から、かかりつけの小児科で月一回の経過観察を続けていたのですが、なかなか発達が見られなかったため、1歳2カ月になったタイミングで療育に通うことを先生から直接薦められ、そのまま紹介状を書いてもらいました。
かかりつけの小児科の先生にはもともと、手足の筋肉発達が弱いから1歳半までに歩けたらいいねと言われていて、私も娘の運動機能の発達に遅れがあることはわかっていたので、療育に通うこと自体はすんなり受け入れられました。
むしろ、1歳2カ月という早い段階専門的な先生に診てもらえることにメリットを感じました。
実際の流れ
ケースワーカーと面談

かかりつけの小児科で紹介状を書いてもらってから、まず、ケースワーカーとの面談を予約しました。
当日の面談自体は約1時間ほどで、面談前にいくつかの書類が渡され、記入してくるように言われました。内容は、療育に関しての同意書と、子どもの成長の様子を可視化するための質問事項がたくさんありました。
面談では、その質問事項に沿って、生まれてから現在に至るまでの心配事や成長の様子をシェアしていく感じで進めらていきました。
私がケースワーカーとお話ししている間は、保育士さんが娘をみててくれ、その場にはおもちゃなどもたくさんあり、娘も安心して遊べている様子だったので、私も安心して面談に集中することができました。
医師との面談

ケースワーカーとの面談のあと、支援センターの医師との面談がありました。
ここでも同じように、今までの娘の様子、現在の成長状況、できることとできないことを説明する形でした。
療育に進む前に、医師から療育の必要判断が出ると、実際に療育サービスが開始しました。
療育開始

いよいよ、療育サービス開始です。
子どものケースに合わせて、月に1~4回、療育の時間が設けられます。
娘はだいたい週に1回のペース。
毎回療育の時間の後に、次の週の空いてる日程や時間を伝えて、それに合わせて時間を組んでくれます。また、理学療法士さんや作業療法士さんなど、さまざまな発達障害にあわせて、サービスを組んでくれるので、子どもに合わせたケアを行ってくれます。
まとめ
- まず紹介状を書いてもらう
- ケースワーカーと面談する
- 支援センター直属の医師と面談する
- 療育サービス予約し、開始
以上が、私の娘の療育サービス開始までの実際の流れでした。
だいたい、療育サービス開始まで1カ月くらいを要しました。もともと、もっとかかるかもと伝えられていたので、思ったよりスムーズだったなという印象です。
地域差はあると思いますが、療育は結構混んでます。
面談してから、サービス開始まで数カ月待つこともあるそうなので、子どもの発達が心配な場合はなるべく早め早めに行動されることをおすすめします。

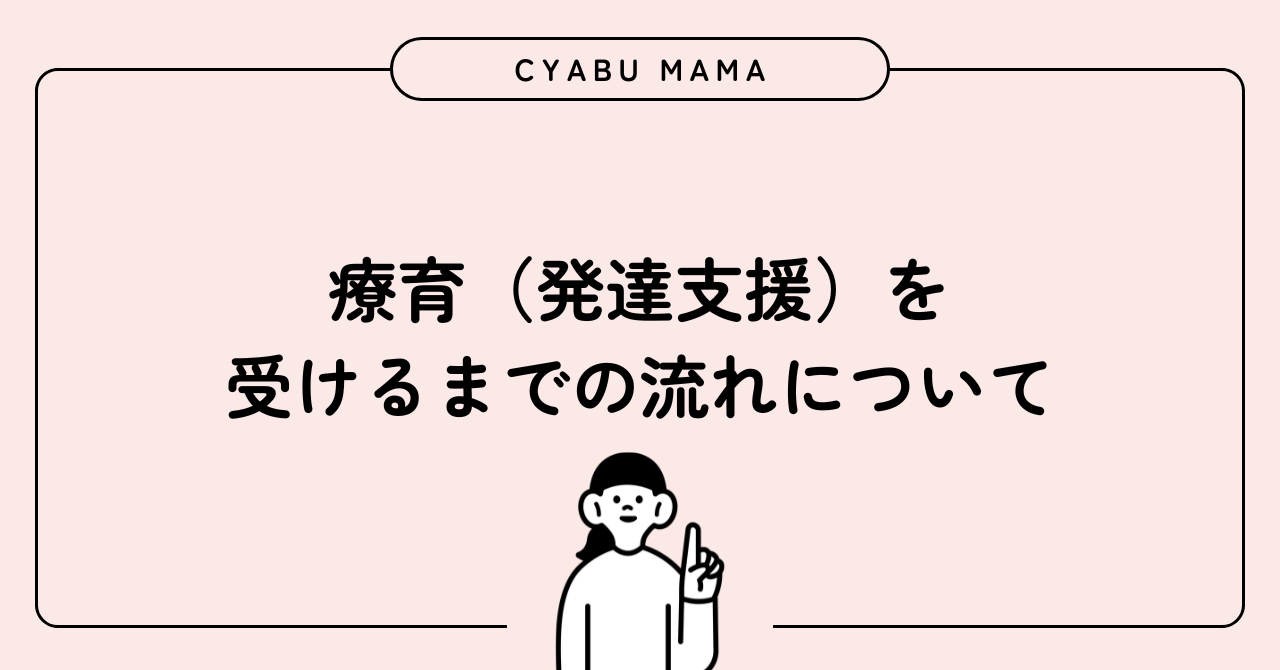
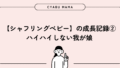
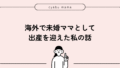
コメント